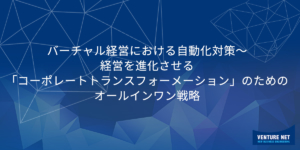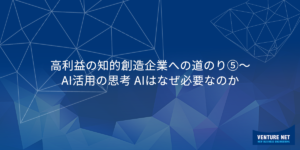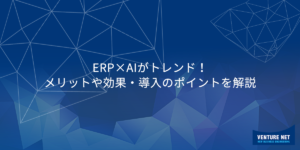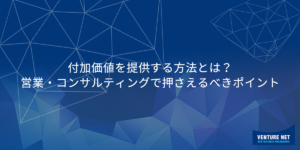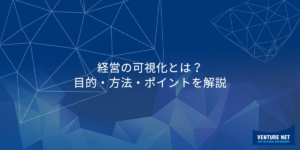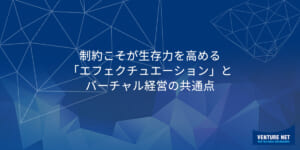これまで、バーチャル経営では経営の自動化をテーマに、個別業務の自動化対策を紹介してきました。自動化は、効率化や生産性向上だけではなくDXへの布石でもあります。また、DXはCX(顧客体験)の向上を見据えた、新たなビジネスモデルの構築から開始することが多いようです。DXを目指すのであれば、CXの最適化にも取り組むべきでしょう。バーチャル経営では、DXを見据えたCX最適化の方法として、ERPと周辺システムの連携(=バックエンドとフロントエンドの連携)を推奨しています。
なぜCX(顧客体験)最適化が必要なのか
CX(顧客体験)の最適化は、近年のビジネストレンドの中でも重要な位置を占めています。では、なぜCXが重視されるのでしょうか。それは次のような理由があると考えています。
「コト売り」は業界の壁を越えて進む
CXが重視される背景には「コト売りへの転換」があります。コト売りは、顧客とつながり続けることで成長していくビジネスモデルであり、顧客とつながり続けるためには、良質なCX(顧客体験)を提供する必要があります。
2010年代の終盤以降、ビジネストレンドは「モノ売り」から「コト売り」へと移行してきました。コト売りとは、いわば体験を売ることです。コト売りは主にBtoCで進みましたが、徐々にBtoBにも波及し始めており、今後はBtoBでもコト売りが一般化していくでしょう。
では、なぜコト売りへの転換が始まったかといえば、「モノ」自体の価値で差を示しにくい時代に突入したからです。技術の進歩により、誰もが先進的な技術の恩恵を受けられる今、高品質・高機能な製品よりも、「必要十分な品質・機能」と「コストパフォーマンス」が重視されるようになったのです。
また、物価の安い国の企業が生み出すコストパフォーマンスに対抗するためには、モノだけの価値ではなく、モノの組み合わせでコト(付加価値)を生み出す必要も出てきました。こうした流れの中、モノ売りの代表的な存在であった製造業でも、コト売りへの転換が進んでいます。その好例が、「製品IoT」です。
IoT製品では、IoTデバイスを工業機械に組み込むことで機械の状況をモニタリングし、そこから得られたデータを整備や改修につなげるといったサービスを提供しています。このように、もはやコト売りはモノ作りの世界にも浸透し始めており、今後はどの業態でも無視できないビジネスモデルなのです。
さらに、CXが重視されるのはコト売りだけではありません。なぜなら、顧客ごとにカスタマイズされた製品を、小ロットから迅速に提供することでもCXは向上するからです。
CX最適化に必要な要素
One to OneマーケティングやABMを推進していくと、「独自の要望を持った顧客」と長く付き合う機会が増えていきます。こうした顧客の期待にこたえ続けるためには、常にCXを最適化するための仕組みが欠かせません。そこで、CXの最適化に必要な要素を整理してみます。
オペレーションレベルの向上
CXを高めるための最もシンプルな方法は「顧客の待ち時間を最小化する」ことです。受注、契約、納期解答などから生じるリードタイムを短縮できれば、それだけでCXは底上げされるでしょう。そのためには、各現場におけるオペレーションレベルの向上が必要です。
迅速で的確な提案
また、顧客の反応に沿った提案を迅速かつ的確に行うことでもCXは向上すると考えられます。マーケティングや商談の場で得られた顧客の反応を、製造の現場にも反映させて素早く新しい製品・サービスを提案する体制が求められます。
フロント、バックオフィスのシームレスな連動
CXの向上には、迅速で的確な提案を支えるためのシステムにも気を配るべきです。具体的には、提供した製品・サービスからフィードバックされたデータを蓄積するシステムや、原材料や製品在庫、製造工程を管理するバックエンドシステムとの連動が必要になるでしょう。端的に言えば、バックエンドシステムの代表格である「ERP」と、CRM・EC・SFAなどのフロントシステムがシームレスに連動することが理想です。
マイクロモーメントとハイパーパーソナライゼーション
近年、BtoBの購買体験にもBtoCに似た施策が必要だと考えられるようになっています。具体的には、「顧客の瞬間的な欲求、意欲、行動を取り込み、意思決定につなげるための施策」です。
BtoBにおいても顧客ニーズの多様化が進んでおり、従来のようなセグメンテーションやターゲティングによる分析のみでは成果に結びつきにくい時代です。そのため、瞬間的な顧客行動をERPに取り込んで製品・サービスに反映させ、実際の店舗にいるかのような比較検討の場を提供し、意思決定を促す必要がでてきました。つまり、Googleが提唱している「マイクロモーメント(何かをしたいという欲求の瞬間)」を的確に捉える仕組みが必要なのです。
しかし、マイクロモーメントを捉えるのは非常に難しく、従来の企業向けITで実現することはほぼ不可能だといって良いでしょう。そこで注目すべきが「ハイパーパーソナライゼーション」です。
ハイパーパーソナライゼーションは「顧客行動をリアルタイムに収集し、顧客要望やニーズに応じてあらゆる製品・サービスをカスタマイズする」という考え方です。マイクロモーメントを捉えるためには、Webサイト、EC,広告、メール、アプリを徹底的にパーソナライズしていく必要があるでしょう。これこそが、今後のERP・CRM・ECシステムに求められる要素であり、CX向上のカギを握っているのです。
ERP+CRMを核とした「統合型CXプラットフォーム」
バーチャル経営では、CX最適化のための仕組みとして「統合型CXプラットフォーム」を推奨しています。統合型CXプラットフォームとは、ERPとCRMを中核に据え、複数のシステムから収集されたデータをバックエンドに素早く反映させて、CXを高める製品・サービスの開発に活かす仕組みです。
ERP+CRMでCX最適化のプラットフォームを構築
統合型CXプラットフォームのコア部分には、「ERP」と「CRM」を据えます。あるいは、この両方の性質をもったクラウドパッケージでもよいでしょう。このコア部分に、SFAやECを結合し、フロントエンドとバックエンドのデータを連動させてCX最適化につながるデータを蓄積していくのです。
統合型CXプラットフォームの強み
統合型CXプラットフォームの強みとしては、次のような点が挙げられます。
- 見積、納期解答、代替提案の迅速化
- アップセルやクロスセルのタイミングを的確に捉える
- 既存顧客との関係性が好転し、LTV最大化を目指せる
- データドリブンによる新たな知見の獲得
- 営業、マーケティング、開発、カスタマーサービス、会計など社内の業務部門が連動し、全体最適の自動化が進む
一言で表すと「CXという軸で社内の全体最適が自動化される」とも言えそうです。これまでバックエンドの中心であるERPは、CXと切り離されたところにありました。しかし、実際に製品・サービスを生み出すためにはERPの力が不可欠であり、この点をCXにつなげることがCX最適化の一歩だと考えています。
バーチャル経営における統合型CXプラットフォーム
バーチャル経営では、統合型CXプラットフォームの実現方法として、「NetSuite+Shopify」を想定しています。ERP・CRMの要素を合わせもつNetSuiteは、そもそも統合型CXプラットフォームに適した製品です。これに、ECプラットフォーム「Shopify」を組み合わせ、EC側から寄せられる顧客の反応をバックエンドに反映させるのです。
また、ベンチャーネットの独自ツール「ABM AUTOMATION」※注を組み合わせることで、顧客ごとに製品ラインナップ・価格・販路を切り替えて表示することができます。「顧客ごとにカスタマイズされた製品を、小ロットから迅速に提供する」ことができるため、CX向上に貢献するでしょう。
さらに、顧客側・事業者側双方にとって面倒な請求支払いの手続きは、「Payment Automation」による自動化を、認知拡大のためのSEO対策については「SEO AUTOMATION」※注を活用します。課題や悩みに対応する高品質なコンテンツを提供しながらERPとデータを連動させ、CXを高める施策に結び付けられると考えています。
※注 現在開発中のため、機能は変更となる可能性があります。
まとめ
ここでは、顧客の反応を素早くバックエンドと共有し、CXを最適化する仕組みとして「統合型CXプラットフォーム」を紹介してきました。CX向上は、優良顧客と狭く深く付き合い続けるための軸になる考え方です。CX向上を軸にしたモノ売り・コト売りは中小企業こそ真剣に検討すべき課題だと思います。次回は、バーチャル経営の具現化「ベンチャーネットエンジン」を紹介します。