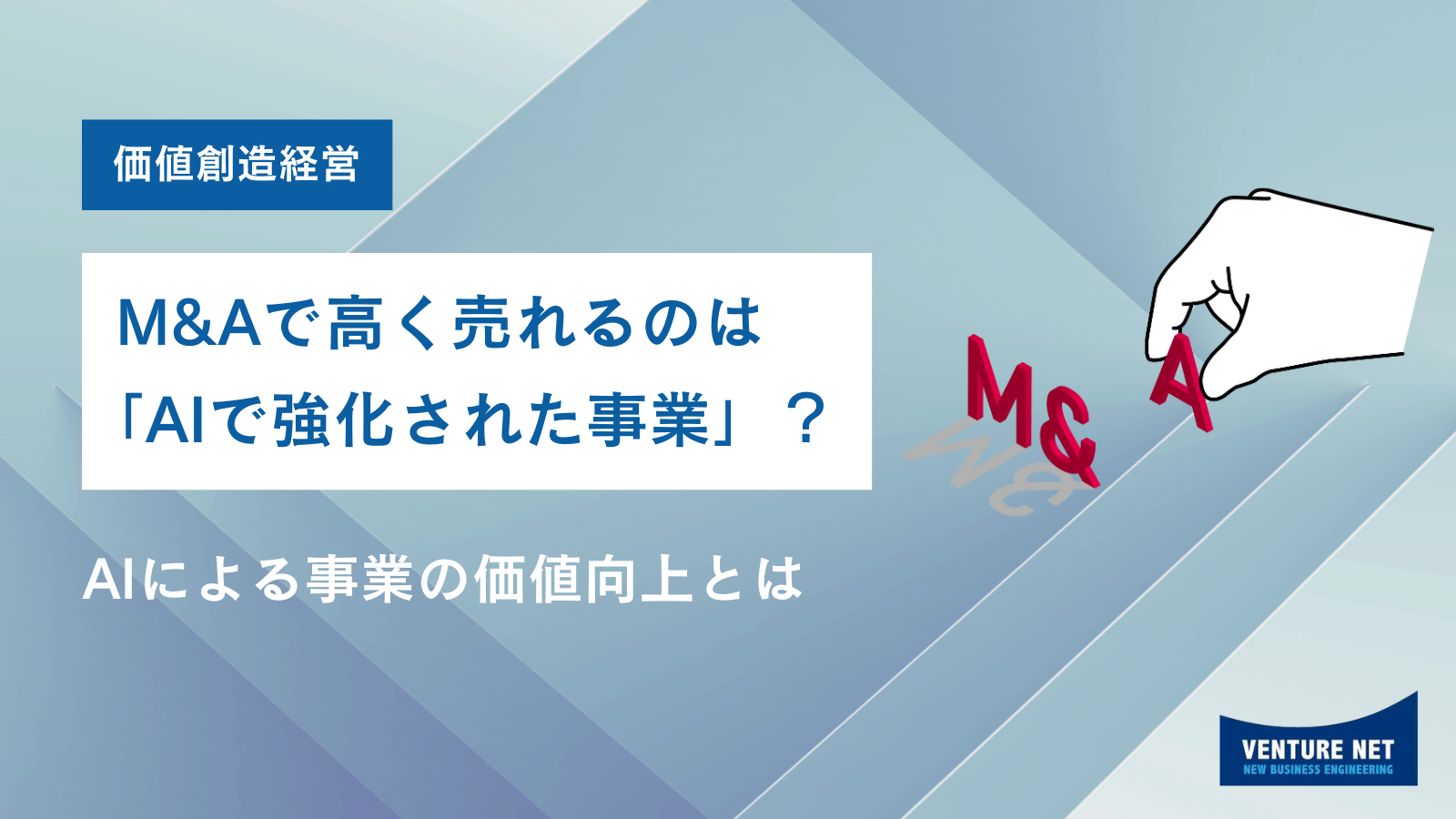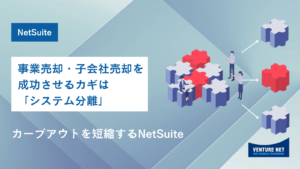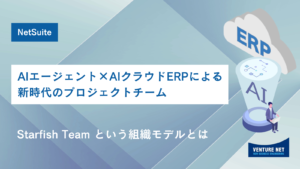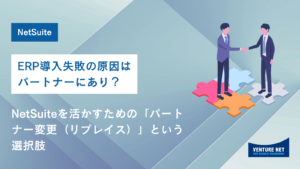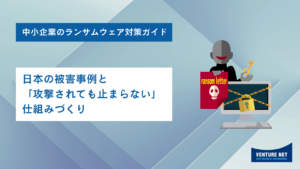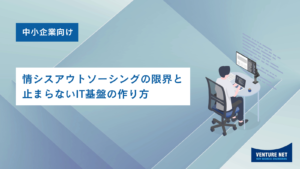「企業価値」は今後の経営に欠かせない視点であり、これを裏付けるように「価値創造経営」という言葉が広まっています。一方で、将来的に事業を売却しようと考えている経営者であれば、「どうすれば事業が高く売れるか」という点が気になりますよね。
「高く売れる事業=価値のある事業」であることは間違いありませんが、現在はその価値に新たな判断軸が登場しています。それは「AI」です。
今回は、「AI」がなぜ事業の価値を底上げするのか、という点について解説します。
M&Aで高く売れる事業の条件
まず、一般論としてM&Aで高く売れる事業の条件を列挙してみましょう。
| 評価項目 | 内容 | 買い手が重視する理由 |
|---|---|---|
| 安定した収益 | 毎年黒字で、売上・利益が安定または右肩上がり | 将来のキャッシュフローを予測しやすい |
| ストック型ビジネス | サブスク・会員制など定期収益が発生 | 継続課金で利益が積み上がる |
| 経営の属人性が低い | マニュアル・標準フローが整備されている | 引き継ぎコストが少なく運営が安定 |
| 再現性・スケーラビリティ | 他地域展開・フランチャイズ化が容易 | M&A後に事業拡大しやすい |
| 顧客基盤の分散 | 特定顧客への依存が少ない | 取引先の喪失リスクが小さい |
| 成長市場への属し | IT、DX、環境、医療など拡大市場 | 中長期で企業価値が伸びる可能性 |
| 独自技術・ブランド | 特許・ノウハウ・認知度がある | 差別化要素として高評価 |
| リスクの少なさ | 訴訟・簿外債務・法務問題がない | デューデリジェンスで減点されにくい |
| インフラ・設備 | IT基盤・施設が整備済み | 買収後に追加投資が不要 |
| 人材と定着率 | 離職率が低くスキル人材が在籍 | 即戦力として活用可能 |
高値で売れる事業に共通する「3つの軸」
これらの項目をさらに整理すると、「安定性」「再現性」「成長性」の3軸に集約できます。
①安定性
黒字経営、分散された顧客基盤、リスク管理の徹底がなされている事業は買い手が付きやすく評価額もあがります。
②再現性
オーナー依存の排除、業務標準化、属人化リスクの低減などは「買った後も運用しやすく、同じように利益を上げられる事業」として評価されます。
誰が経営しても同じ成果を出せる体制が整っている企業ほど、引き継ぎ後の不確実性が小さくなります。
③成長性
拡張可能なビジネスモデルや成長市場への参入状況などは「将来的な価値が高い」とみなされます。特にITやSaaSのように「仕組みでスケールできる」事業は、将来キャッシュフローを評価されやすいです。
以上3つの要素がそろっていれば、M&Aによる事業売却は高確率で成功するでしょう。
しかし、実際にはこれら3つがそろった状態で事業を手放すケースは稀です。
特に①が満たされている状況ならば、売却する理由そのものが発生しないこともありますよね。
そこで、②と③を強化し、①に多少の難がある状態でも事業を高値で売るという戦略に切り替えてみましょう。
経営体制の透明化、業務の標準化、データによる意思決定が進んでいるほど、買い手はリスクを小さく見積もります。
生成AIで強化・整理された事業はM&Aしやすい
「再現性」と「成長性」を効率的に整備できる手段として、近年は生成AIの活用が注目されています。
生成AIは、企業のナレッジや業務プロセスを可視化し、再現性のある経営を可能にします。
買い手にとっても、AIを適切に組み込んだ事業ほど、「完成された仕組み」として映るのです。
属人性の排除で引き継ぎが容易に
中小企業のM&Aでは、「社長しか分からない」「担当者が辞めたら事業が止まる」という属人化が最も大きな障壁になります。
一般的にはM&A後の統合作業(PMI)で補完されますが、それでもリスクはゼロになりません。
生成AIが適切に導入され、営業ノウハウや業務マニュアル、問い合わせ対応などが自動化されていればこうしたリスクは非常に小さくなります。
ドキュメント・ナレッジの資産化
AIによって生成・整理されたマニュアルや提案書、FAQ、顧客対応履歴などは「形式知」として残ります。
これはM&Aのデューデリジェンスにおける大きな評価対象です。
属人化しがちな情報がデータベース化されていれば、買収後の運営やPMI(統合プロセス)がスムーズに進むからです。
また、初期教育コストや引き継ぎ期間を短縮できるため、買い手にとっての負担も軽くなります。
AIによる利益率の改善
生成AIの導入は、財務面にも効果をもたらします。
なぜなら顧客対応や営業資料作成をAIが支援することで、社員1人あたりの生産性が向上するからです。
さらにバックオフィス業務の自動化では、人件費やオペレーションコストが削減され、利払い前・税引き前・減価償却前利益(EBITDA)の改善が見込めます。
M&AではEBITDAが価値算定の基準になるため、売却価格の上昇につながります。
データ活用力の高さが「将来性」として評価される
現在のM&A市場では、データドリブンな経営体制の有無を重視するケースが増えています。
生成AIを導入している企業は、顧客データや購買履歴、問い合わせ内容といった非構造データを整理・活用できる状態にあります。
データドリブン経営が必須になりつつある中で、この「データ活用力」は「成長余地がある会社」として評価されます。
AIを活用した需要予測、顧客分析、価格最適化が可能であれば、買収後の事業成長を定量的に見通せるからです。
買い手以上のAI導入レベルは「差別化」になる
M&Aの相手方として資金力のある大手企業を想定する場合は、「AI導入レベル」がさらに重要です。大手企業ほどAI投資が進んでおり、AI導入レベルの低い事業は今後価値を下げる恐れがあります。
一方で、買い手企業よりも高いレベルでAIを活用している事業は、すぐに収益化できる「完成されたプラットフォーム」として評価されるわけです。
PMI(統合)の容易さと「最適化」へのつながり
生成AIによって情報の統一や暗黙知の可視化が進むと、M&A後の統合作業もスムーズになります。
社内ルールや商流、コミュニケーションの差異が明文化されているため、合併後の摩擦が少なくて済むからです。
さらに、AIで整理されたデータを量子アニーリングなどの最適化技術と組み合わせれば、拠点統廃合や人員配置、在庫調整などの最適解を高速に導けます。
これはM&A後の経営統合における「最適化経営」の第一歩といえます。
事業売却のために基幹システムを強化~NetSuite関連サービス
ここまで、M&Aで事業を高く売るためのポイントについて解説してきました。
弊社ではこうしたトレンドを踏まえ、「確固たる事業データの運用基盤」と「M&A後の最適化」「価値創造のための最適化」などにフォーカスしたサービスを提供しています。
・経営企画サポートCOO代行サービス
NetSuiteと生成AIを組み合わせ、迅速で正確な経営判断をサポート
https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/netsuite-ai/
・M&A、PMIコンサルティング
NetSuiteに蓄積されたデータを元に、財務会計から業務プロセスまでを統合
https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/netsuite-ma-pmi/
・NetSuite×量子アニーリングで最適化をサポート
量子コンピューティングの中でも「組み合わせ最適化」に特化した量子アニーリングを活用し、さまざまな経営課題の解決をサポート
https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/netsuite-vnengine/
まとめ
今回は、近年のM&Aで重視される「再現性」「成長性」を強化する方法として、NetSuiteと生成AIの活用を紹介しました。M&Aで事業売却を成功させるには、ERPなどで「データドリブンな経営基盤」を作りつつ、生成AIや量子アニーリングといった先端技術で「価値を上げる」ことが重要になると考えています。
もしNetSuiteを核とした各種サービスにご興味があるようでしたら、お気軽にお問合せください。